・ 相続税がかからない財産ってあるの?
・ 債務の取り扱いはどうなるの?
こんな疑問を解決します。
✔ 本記事の内容
・ 非課税財産の解説
・ 債務の取り扱いを解説
✔ 本記事の信頼性
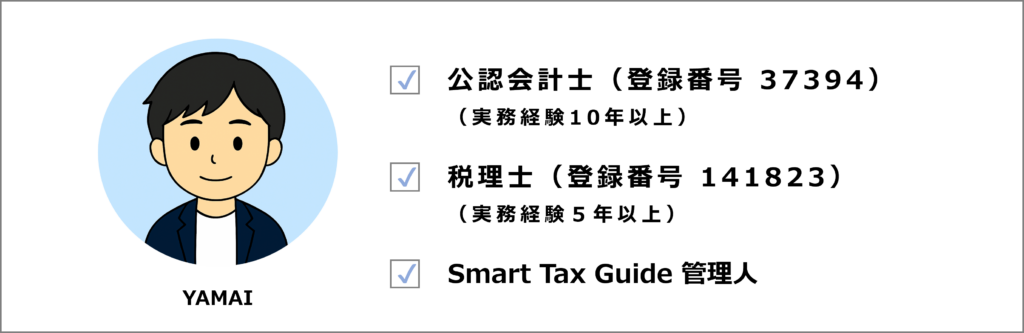
10年以上の実務経験を活かしてシンプルでわかりやすい解説を心がけています。
今回は、「相続財産の種類と範囲」を解説してきます。
本記事では、相続税の課税財産、非課税財産、債務控除について、初心者にも分かりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
それでは、相続財産の種類と範囲についての解説をはじめていきます。
1. 課税財産とは何か

相続税の課税財産とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で所有していた財産のうち、相続税法に基づいて課税の対象となるものをいいます。
課税対象となる財産には大きく4つの区分がありますので、まずはこちらを解説していきます。
課税財産の区分
課税財産は大きく以下の4つの区分に分けられます。
| ① 本来の財産(民法に基づき相続・遺贈・死因贈与で取得した財産) ② みなし相続財産(相続税法により相続または遺贈で取得したものとみなされる財産) ③ 相続開始前3~7年以内の暦年課税による贈与財産 ④ 相続時精算課税による贈与財産 |
① 本来の財産(民法に基づき相続・遺贈・死因贈与で取得した財産)
被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を、民法のルールや遺言、生前契約に基づいて引き継ぐ財産になります。代表例としては預金、株式、建物、土地など故人が所有していた固有の財産が該当します。
② みなし相続財産(相続税法により相続または遺贈で取得したものとみなされる財産)
故人の固有の財産には該当しませんが、相続税法によって本来の財産と同様に取り扱われる財産になります。代表的なものとして生命保険金や死亡退職金などが該当します。
③ 相続開始前3~7年以内の暦年課税による贈与財産
生前に相続開始前3年~7年以内に贈与されていた財産になります。生前の贈与であっても、相続時に相続税が課されますが、同時に支払済みの贈与税も考慮され最終的な相続税負担分が計算されます。なお、改正による経過措置の影響のため「3年~7年以内」という表現にしています。
④ 相続時精算課税による贈与財産
生前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産になります。
この制度を適用すると贈与時に2,500万円の非課税枠使用できますが、相続時に相続税の計算に組み入れられ精算されます。
課税財産の評価基準
相続税の計算では、取得した財産の価値を金額で評価する必要があります。
この評価は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)の時価を基準とし、国税庁が定める財産評価基本通達などの評価基準に従って行います。
財産の種類によって評価の方法が異なり、それぞれ定められたルールに基づいて正確に金額を算出することが重要です。
2. 本来の財産
本来の財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた現実の財産を指します。
現金・預貯金・不動産・有価証券など、相続人が実際に引き継ぐことになる財産が対象となります。
ここでは相続税の計算上、課税対象となる本来の財産の代表例を紹介します。
✔ 本来の財産の代表例
▪ 預貯金
被相続人所有の現金や預金が該当します。
名義上は配偶者や子どもなど他人になっているものの、実際には被相続人が拠出・管理していた預金は「名義預金」を呼ばれ、被相続人の財産に該当するの留意が必要です。
預貯金は相続開始日時点の残高をもとに評価し、定期預金の場合は相続発生日に解約した場合の金額で評価されます。
▪ 上場株式
被相続人が証券口座に保有している上場株式が該当します。
上場株式は相続開始日前後の株価のうち、一定の算出方法により計算した価格により評価します。
▪ 非上場株式
上場株式以外の未上場の株式でが該当します。
上場株式とは異なり時価が観察できないため、会社の財務状況や業種等に応じ、「類似業種比準方式」「純資産価額方式」など一定の評価基準に基づき評価します。
▪ 貸付金・未収金・売掛金
知人等への貸付金、事業で発生した売掛金、未収入金などの債権も該当します。
回収不能な部分を除き額面で評価します。
▪ 土地等
被相続人が所有する土地や土地に関連する権利が該当します。
土地等は「路線価方式」、「倍率方式」その他一定の方法で評価します。
▪ 建物
被相続が所有する自宅や賃貸用の建物等が該当します。
固定資産税評価額を基準一定の計算のもと評価します。
3.みなし相続財産
みなし相続財産は、相続税法によって本来の財産と同様に取り扱われる財産です。
代表的なものとして生命保険金や死亡退職金などが該当します。
ここではみなし相続財産の代表例を紹介します。
✔ 生命保険金
生命保険金とは、被相続人(亡くなった方)の死亡をきっかけに支払われる保険金のことです。
このうち、保険契約者・保険料負担者が被相続人だった場合、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また生命保険金には、相続税がかからない非課税枠が設けられています。
| 非課税枠の計算ルール この非課税枠は、以下の計算式で求められます。 500万円 × 法定相続人の数 実際の受取人の数ではなく、「法定相続人の数」で計算する点に注意が必要です。 【具体例】 この場合の非課税枠は以下のように計算されます。 つまり、3,000万円のうち1,500万円は非課税で、残りの1,500万円が相続税の課税対象となります。 |
生命保険は、保険料負担者や被保険者が被相続人ではない場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課されることになりますので、課税関係の確認をすることが重要です。
✔ 死亡退職金等とは
死亡退職金とは、被相続人(亡くなった方)が勤務先に在職中に亡くなったことにより、勤務先から遺族に支給される退職金や功労金のことをいいます。
|
非課税枠の計算ルール 【具体例】 したがって、2,000万円のうち1,500万円は非課税となり、残り500万円が相続税の課税対象になります。 |
死亡退職金が遺族への弔慰金や見舞金として支給された場合でも、金額や会社規程の内容によっては課税対象となることがあります。
明確な規定がない場合、通常の退職金とみなされ課税対象になるケースもあるため注意が必要です。
また、在職中に退職が決まっていた場合など、死亡が支給の原因でない場合には、みなし相続財産にならないこともありますので注意が必要です。
4.非課税財産
非課税財産とは、相続によって取得しても相続税がかからない財産のことです。
社会的配慮や政策的な理由により、一定の財産については課税対象から除外されます。
ここでは、相続税の計算で非課税とされる代表的な財産の例を紹介します。
✔ 墓所、霊びょう及び祭具など
お墓や仏壇、位牌などの祭具は、生活に根付いた宗教的・慣習的財産として相続税の対象外です。
ただし、投資目的や換金可能な美術品的価値のある仏具などは課税対象になる場合があります。
✔ 相続人が取得した生命保険金や退職手当金のうち一定額
みなし相続財産の例でも紹介したように、生命保険や退職手当金のうち「500万円 × 法定相続人の数」の金額だけ非課税となります。
例えば、相続人が妻と子2人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税となります。
このように、非課税財産は適用条件を正しく理解することで、相続税を大きく軽減することができます。
特に生命保険金や死亡退職金の非課税枠は、非課税金額が大きくなるので相続税の計算上重要なポイントになります。
5.債務
相続税の計算では、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務や支払い義務のある費用については、相続財産の総額から差し引くことができます。
これを「債務控除」といい、実質的な遺産の正味額(課税対象)を計算する上で重要な仕組みです。
正しく債務控除を行うことで、課税額を大きく減らせることがあります。 ここでは、債務控除の対象となる代表的なパターンをご紹介します。
✔ 被相続人の借入金
故人が生前に負っていた借入金は債務として控除が可能です。
金銭消費貸借契約書や返済履歴など、債務の存在を証明できる資料を準備することが重要です。
✔ 未払税金・未払費用
相続開始時点でまだ支払っていなかった所得税、住民税、固定資産税などの税金や、医療費・介護費などの未払金も控除の対象です。
病院の請求書や税務署からの納付書などを確認しましょう。
✔ 葬式費用
被相続人の死亡に伴い、通夜・告別式・火葬・埋葬などにかかった費用は控除可能です。
ただし、香典返しや墓石の購入費用は、生活保持のための費用とみなされ、控除対象外となります。
このように、債務控除は相続税を正しく計算するうえで非常に重要です。 医療費や税金など「見落としやすい債務」も多いため、しっかりと支出内容を整理し、証拠書類を揃えておくことが大切です。
6.まとめ
ここまで、相続税の課税財産、非課税財産、債務控除の考え方について解説してきました。
最後に、重要なポイントを整理して振り返っておきましょう。
|
今回のまとめ ✅ みなし相続財産の取扱い ✅ 非課税財産 ✅ 債務控除の仕組み |
相続税対策は早めの準備がカギ!
特例や非課税枠、控除制度を上手に活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
正しい知識を持ち、専門家の力も借りながら、安心できる相続の準備を進めましょう。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。


コメント