・ 計算方法や申告のルールも難しくて、よくわからない…
・ 初心者でも理解できるように、シンプルに解説してほしい!
こんな疑問を解決します。
✔ 本記事の内容
・ 相続人の範囲と相続税の納税義務
・ 相続税の計算方法と申告の流れ
✔ 本記事の信頼性
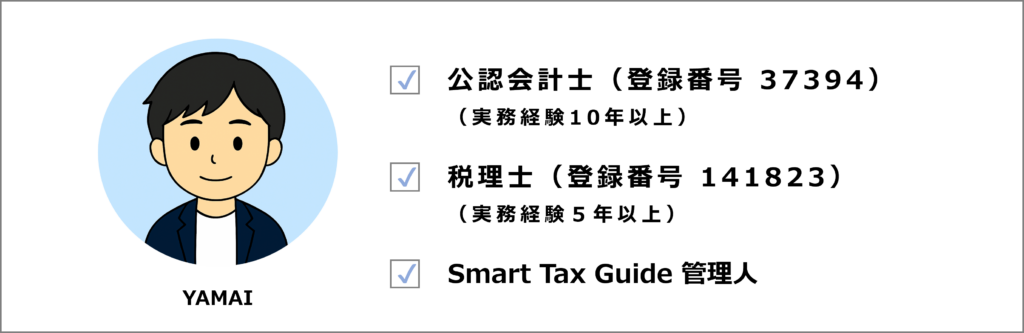
10年以上の実務経験を活かしてシンプルでわかりやすい解説を心がけています。
今回は、「相続税の基本的な仕組み」を解説してきます。
しかし、基本的な仕組みを理解すれば、必要な手続きや申告の流れがぐっと分かりやすくなります。 この記事では、相続税のポイントをシンプルに解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
それでは、相続税の基本的な仕組みの解説をはじめていきます。
Contents
1. 標準的なタイムスケジュール

相続が発生すると、様々な手続きが期限付きで求められます。
ここでは標準的な相続手続きのスケジュールを示しながら実施するべき相続手続について解説をしていきます。
「今何をすべきか?」を時系列で確認しながら、期限を逃さずに手続を進めていきましょう。
STEP1:7日以内にやるべきこと
✔ 死亡届の提出
被相続人が亡くなったことを市区町村に届け出るのが「死亡届」です。
死亡日から7日以内に、亡くなった方の本籍地・届出人の住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場に提出します。
なお、火葬許可と合わせて死亡届の提出も葬儀屋で代理手続をしてくれることもあります。
STEP2:速やかにやるべきこと
✔ 遺言書の確認(亡くなる直前、死亡危急者の遺言の場合)
相続が開始されたら、速やかに遺言書の有無を確認することが重要です。
法定相続割合に基づかないケースもありますが、遺言の内容は尊重される必要がありますので、可能な限り速やかに確認し相続トラブルを防ぐことが重要です。
なお「死亡の危急に迫った場合」の口頭や簡易な遺言は、20日以内に家庭裁判所へ請求し確認することが必要になりますので注意が必要です。
STEP3:3ヶ月以内にやるべきこと
✔ 相続の承認と放棄
相続人は、相続の放棄や限定承認(財産を限定的に相続すること)が可能です。
この場合、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出することが求められています。
なお、単純承認(すべての財産と債務を引き継ぐこと)の場合は特段手続をせずとも単純承認されたものとみなされます。
限定承認:財産の範囲内で債務を負担することを言います(相続人全員での申請が必要)
相続放棄:相続財産・債務を一切引き継がないことを言います(家庭裁判所への申述が必要)
STEP4:4ヶ月以内にやるべきこと
✔ 所得税の準確定申告
故人である被相続人が個人事業主であった場合や不動産所得があった場合等は、、死亡の年 の1月1日から死亡日までの間に所得の確定申告が必要になります。
これを準確定申告と言います。
準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が行うこととなっています。
なお、前年分の確定申告書を提出しないで1月1日~3月15日の間に死亡した場合、前年分の確定申告は本年分の準確定申告と同じく相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が行うこととなっています。
✔ 消費税の準確定申告
消費税の場合も同様に、被相続人の基準期間(相続が起きた年の前々年)における課税売 上高が1,000万円を超える場合には、 1月1日から相続の開始の日までの期間について相続の開始があった日の翌日から4か月以内に消費税の準確定申告が必要となります。
STEP5:10ヶ月以内にやるべきこと
✔ 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って「誰が何を相続するか」を決める手続きになります。
相続税の申告・納付期限が被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内であるため、遺産分割協議も自動的に同じ期限内に実施すべきものと整理されます。
なお、遺産協議がまとまらない場合を考慮し、未分割の場合の申告が認められています。
✔ 相続税の申告・納付
相続税の申告書は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが課される場合がありますので注意が必要です。
なお、提出期限が土日祝日の場合は、翌営業日が期限日となります。
STEP6:1年以内にやるべきこと
✔ 遺留分侵害額の請求権の行使期限
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても侵害することができない最低限の取り分が保障されています。
これを遺留分と言います。
兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとあり、1年以内に侵害分の支払いを請求する必要があります。
なお相続開始の時から10年を経過した際にも時効により消滅すると定められています。
これらの期限を過ぎると、権利行使することができなくなるため注意が必要です。
STEP7:3年以内にやるべきこと
✔ 未分割の場合の分割期限
相続税の申告・納付期限内に遺産分割協議が整わなかった場合、法定相続分により申告・納税することが求められています。
その場合、提出期限から3年以内に分割される見込みである旨の申請書を提出することになっており、原則として期限後3年以内に遺産の分割を実施しない場合、税額控除等の特例制度を受けることができなくなります。
なお提出期限から3年以内に分割されなかった場合であっても、提出期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に一定の申請書を提出し承認を受けることで、特例の適用を受けることが可能です。
2. まとめ
ここまで、標準的なタイムスケジュールのもとで実施する手続 について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。
|
今回のまとめ ✅STEP1 7日以内 死亡届の提出 |
相続の手続きは、期限や必要書類、そして条件などが細かく定められています。
「気づいたときには手遅れ…」とならないためにも、早めに情報を整理し、必要に応じて専門家に相談することがとても大切です。
ぜひ本記事を参考に、相続発生後の流れと期限をしっかり把握し、ご家族が安心して相続を迎えられるよう、準備を進めていきましょう。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。


コメント